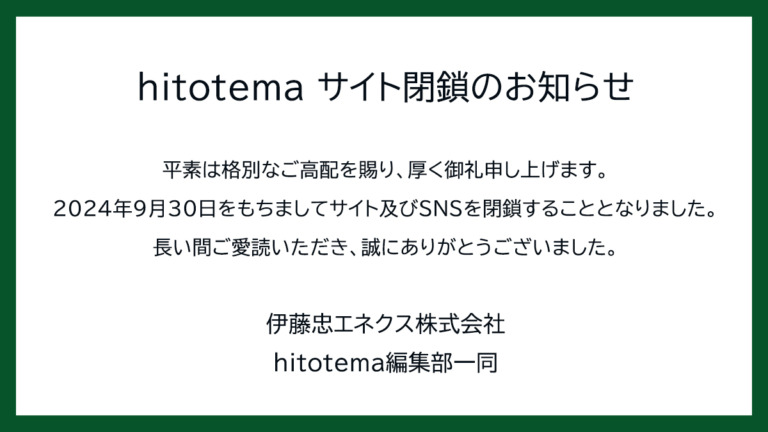酸素系漂白剤は単に漂白するためのものだと思っているかもしれませんが、実はさまざまな用途があります。ですが、どんなときに使い、どんな効果があるのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、酸素系漂白剤の特徴と正しい使い方を解説していきます。
目次
酸素系漂白剤とはどんな洗剤?
酸素系漂白剤には粉末タイプと液体タイプの2種類があります。名前は同じでも実は成分がまったく異なり、使い方にも違いがあるため目的によって使い分けなければなりません。
では、それぞれの特徴とほかのアルカリ性洗剤との違いを見ていきましょう。
粉末タイプの酸素系漂白剤

粉末タイプの酸素系漂白剤の主成分は過炭酸ナトリウム。アルカリ性で水に溶けやすいのが特徴です。お湯に溶かすことで発生する酸素の泡で汚れを分解してくれます。
液体タイプよりも漂白力が高く、掃除と洗濯に使えます。但し、ウールやシルクなどの天然タンパク質繊維でできた素材に使ってしまうと素材そのものにダメージを与えてしまうため、こういった素材の洗濯での使用は避けてください。
塩素系漂白剤のようにツンとしたニオイがないため、キッチンの漂白剤としても安心です。カビ取りや油汚れにも強く、除菌や消臭効果があります。
酸素系漂白剤としては「オキシクリーン」や「シャボン玉・酸素系漂白剤」が有名です。
液体タイプの酸素系漂白剤

液体タイプの酸素系漂白剤の主成分は過酸化水素。粉末タイプがアルカリ性なのに対し、液体タイプは弱酸性です。そのため、皮脂や油汚れは落とせません。
掃除には不向きで、洗濯物のシミやくすみを取るために使います。弱酸性ですから、粉末タイプでは使えないウールやシルクの洗濯にも使用可能です。
名称が似ている塩素系漂白剤と間違えやすいので、購入する際は表示を必ず確認しましょう。
重曹やセスキ炭酸ソーダとの違い
粉末の酸素系漂白剤は重曹やセスキ炭酸ソーダと同じアルカリ性です。この3つの違いはpH値の度合い。アルカリ度の強さは酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)>セスキ炭酸ソーダ>重曹となっています。
それぞれ得意分野があるため、汚れに合った使い分けをしましょう。
| 重曹 | 研磨作用、消臭 | 鍋の焦げつき、茶シブ、まな板のニオイ |
| セスキ炭酸ソーダ | 油や皮脂の汚れ落とし、ヌメリ取り、消臭 | コンロや換気扇の掃除、プラスチック容器のヌルつき、冷蔵庫の掃除 |
| 酸素系漂白剤(粉末) | 漂白、除菌、消臭 | 衣類の漂白、食器の漂白、排水口の掃除、茶シブ |
大掃除の時期になると、ネットや雑誌などで紹介される「重曹」「クエン酸」「セスキ炭酸ソーダ」。ちょっと気になりますよね。けれども、実際にやろうとしても、どこに何を使ったらいいのか分からない方も多いと思います。 キッチンは食べ物を扱うの[…]
酸素系漂白剤(粉末タイプ)の用途

粉末タイプの酸素系漂白剤は、お湯で溶かして使うのが一般的です。50度ほどのお湯がもっとも効果を発揮します。
掃除と洗濯に使えるため、用途はさまざま。それぞれの使い方を見てみましょう。
掃除
酸素系漂白剤はお湯に溶かして「つけ置き」に向いています。
キッチン
シンク、排水口の掃除、ふきんや食器の除菌・漂白に。
お風呂
風呂釜に酸素系漂白剤を入れたお湯を追い焚きし、浴室小物を入れて2〜3時間放置するだけ。軽くこすれば簡単に汚れが落とせます。
洗濯槽
洗濯槽に酸素系漂白剤を500gほど入れてお湯を高水位まで溜めます。2時間ほど放置したあと、通常コースで運転すれば洗濯槽の石鹸カスやカビがキレイになります。
洗濯
酸素系漂白剤は洗濯にも使えます。使い方は2通り。
通常の洗濯
洗濯洗剤を使用して洗濯するときに、さらに大さじ1杯ほどの酸素系漂白剤を加えて洗濯機を回します。
酸素系漂白剤だけを使っても洗浄効果は期待できません。洗濯洗剤と併用することで、通常の洗濯よりも黄ばみや黒ずみが落ちやすくなります。
染み抜き
2Lのお湯に大さじ2杯の酸素系漂白剤を投入し、30分ほどつけ置きします。ひどい汚れの場合は1時間以上つけておくのがおすすめです。その後、通常どおり洗濯すればキレイになります。
酸素系漂白剤(粉末タイプ)のキッチンでの使い方

酸素系漂白剤はキッチンのどこでどのように使えるのでしょうか?
用途別に紹介していきます。お風呂や洗面所の掃除にも応用できます。
シンクの掃除
キッチンのシンク全体にお湯を溜め、酸素系漂白剤を入れるとシンクの掃除ができます。
やり方は以下のとおり。
1排水口から水が流れ出ないようにフタをする。
2酸素系漂白剤を100g程度入れる。シンクの大きさによって量を調節しましょう。
3お湯をシンクの8割程度まで入れる(酸素系漂白剤の量が適切であれば泡立つ)。
4そのまま1〜2時間放置。
5フタをとりお湯が排水されている間にスポンジでシンクをこする。
6シンクを洗い流す。
お湯を入れるタイミングで食器や調理器具を入れ、つけ置きすると掃除と除菌・漂白が同時にできて効率的です。
排水口の掃除
排水口の掃除、除菌・消臭にも適しています。 排水口やパイプの掃除のやり方は以下のとおりです。
1排水口(あるいはパイプ)の中に酸素系漂白剤を小さじ1杯入れる。
2コップ1杯ほどの水を流す。
3そのまま1〜2時間放置。
4最後に洗い流す。
キッチンの排水口の受け皿や三角コーナーなどの掃除のやり方は以下のとおりです。
1受け皿や三角コーナーのゴミをあらかじめ取り除いておく。
2洗い桶あるいはシンクにお湯を溜め、酸素系漂白剤を適量入れる。
3そのまま1〜2時間放置。
4スポンジで軽くこすりながら洗い流す。
シンクのつけ置き掃除のときについでにやってしまっても問題ありません。その場合は、水漏れしないよう水を入れたビニール袋を排水口にはめてフタをしてください。但し、ふきんや食器と受け皿を同時につけ置きするのは不衛生なのでやめましょう。
ふきんや食器の除菌・漂白
酸素系漂白剤は、ふきんや食器の除菌と漂白に使えます。赤ちゃんの哺乳瓶の除菌にもおすすめです。
やり方は以下のとおり。
12Lのお湯(50度以下)を入れた洗い桶に酸素系漂白剤を大さじ2杯入れる。
2洗い桶にふきんや食器を入れて30分程度放置する。
3よくすすぎ、乾かす(ふきんは干す)。
茶シブ取り
酸素系漂白剤は、急須や麦茶ポット・水筒などの茶シブを取るのにも使えます。やり方はふきんや食器と同じ。
水筒の中をキレイにするだけなら、以下の方法でもOKです。
1中に酸素系漂白剤を小さじ1杯程度入れたらお湯をいっぱいになるまで注ぐ。
2しばらく放置。
3よくすすぎ、乾かす。
*重曹でも代用できます。
暑くなってくると麦茶ポット(冷水筒、ピッチャーとも言います)の出番が多くなりますよね。また、最近は節約意識が高くなり、水筒を持参する人が増えてきました。 (画像出典)PIXTA そんな麦茶ポットや水筒の収納場所は決まっています[…]
酸素系漂白剤(粉末)を使うときの注意点
酸素系漂白剤はナチュラル洗剤のひとつとはいえ、取り扱いに注意しなければならない点もありますのでいくつか挙げていきます。
素手での使用を避ける
酸素系漂白剤アルカリ性で皮脂汚れに強く、手荒れの原因になりますので、直接手に触れるのは避け、掃除用の手袋を使用しましょう。
熱湯は使用しない
水よりもお湯のほうが効果的ですが、熱湯は避けてください。素材を傷めたり、火傷したりする恐れがあります。適温は40〜50度です。
使用できない素材がある
また、素材によっては酸素系漂白剤がNGのものがあるので注意してください。アルミ製のレンジフードや自然・大理石の調理台などの掃除には使えません。
保管方法に注意
容器に入った酸素系漂白剤に水分が付着すると、小さな酸素の泡が発生して容器が膨らみ、破裂する恐れがあります。保管するときはしっかりフタをし、水分がかからないようにしましょう。
また、粉の状態でもわずかな酸素が発生するため、密閉容器はNGです。
酸素系漂白剤の正しい使い方を覚えよう

酸素系漂白剤にはさまざまな用途があり、掃除にも洗濯にも大活躍してくれるナチュラル洗剤です。正しい使い方を覚えれば、専用洗剤を使わなくても十分に汚れを落とせます。
お湯の温度さえうまく調節できれば使い方は難しくありません。ぜひ活用してみてください。
重曹は洗剤として日常のお掃除に使える便利なアイテムです。 ところが、「重曹を使っても意外と汚れが落ちない」「重曹を使ったら変色してしまった」といった声も聞かれます。それは正しい使い方をしていないせいかもしれません。 そこで今回[…]
掃除用としても食用としても使えるクエン酸。掃除用のクエン酸は100円ショップでも購入でき、身近な洗剤として使われています。 ですが、クエン酸にどのような効果があって、どんな掃除に向いているのかをよく知らずに使ってしまい「汚れが落ちな[…]
身近にあるナチュラル洗剤の1つである「セスキ炭酸ソーダ(通称セスキ)」。定番アイテムなので多くの人が上手に使いこなしていると思いきや、 「買ってみたものの、どんな掃除に使ったらいいのかわからない」「ちゃんと汚れが落ちない」 と[…]