近年は、共働きしている夫婦や習い事をしている子どもが多く、家族が揃って食事をする機会が少なくなっています。逆に、子どもだけで食事をする「孤食」が増えています。孤食は、子どもの心と身体の成長に大きく関わってきます。
今回は、子どもの孤食の影響や対策について解説していきます。親と子が共に忙しく、一緒に食事をする時間がなかなか確保できないことで悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。
近頃は歯医者さんでも食育の活動をしているところが増えてきています。 歯医者さんと食育はどういう関係があるの?そもそも、何をするの? と疑問に思っている方もいるでしょう。そこで今回は歯医者さんで行う食育について解説していきます。[…]
目次
親がいても起きる孤食・子食とは?

孤食とは1人で食事を摂ることを指す造語で、主に食育に関する話題でよく使われる言葉です。
大人ならともかく、親と暮らしている子どもが「孤食」とは意外に思えるかもしれません。
しかし、家族がいても孤食は起きます。例えば、家事や用事などを親がしている間に子どもだけで食事をするケースです。忙しい時に「先に食べててね」と親は子どもだけの食事を準備して一緒に食べないこともありますよね。
そうなると、子どもが1人で食事をする孤食と変わらない状態になることも。親子のコミュニケーション不足になったり、子どもが寂しさや不安を感じやすくなったりするという影響が指摘されています。
また、習い事などの関係で孤食になることもあります。このケースでは時間がないことが多いので、すぐに食べられるようなパンや、子どもの好きな食べ物だけで済ませてしまい、栄養も偏りがちです。
また、きょうだいがいるから孤食ではないけど子どもだけ、という状態は、「子食」と呼びます。話し相手はいるものの、子どもだけで食事ではやはり好きなものだけを食べがちですし、正しい食事のマナーも身に付きにくくなります。
孤食・子食で起きる子どもへの4つの影響
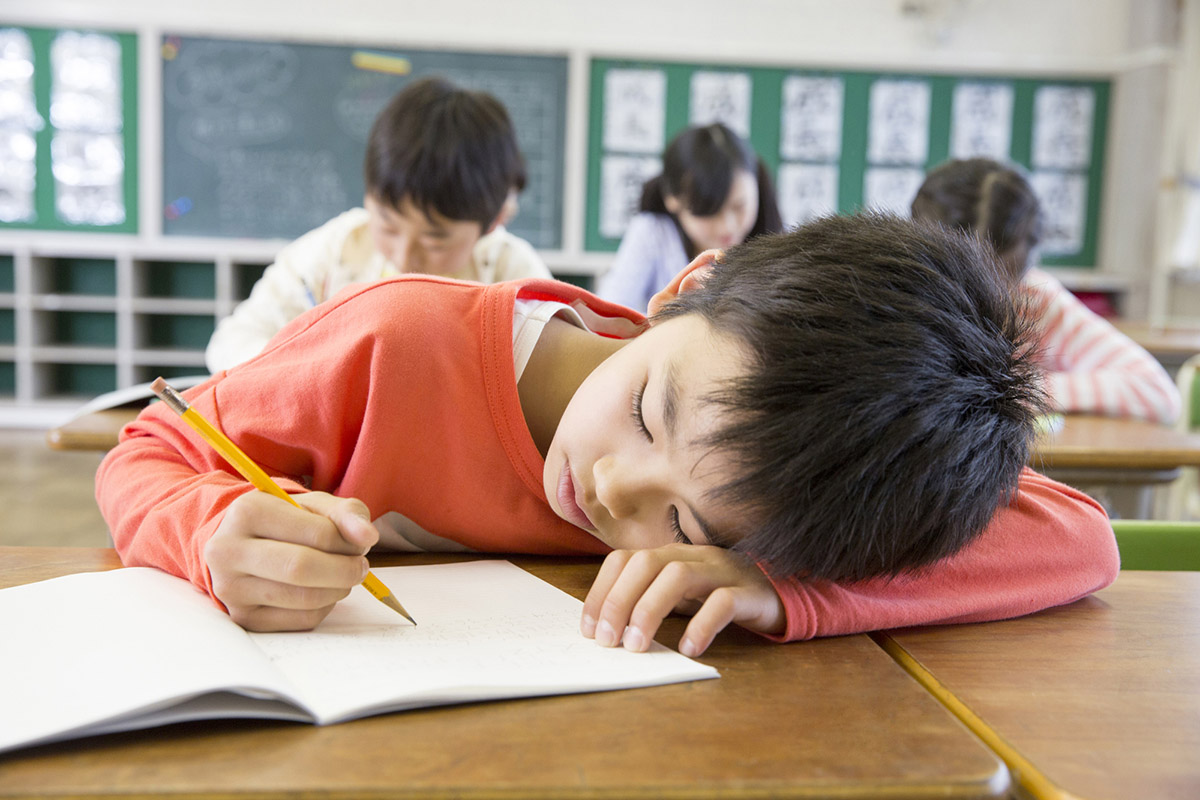
孤食、子食が絶対にダメなわけではありません。
しかしそれが習慣になると、次の4つの影響が子どもに出る可能性があります。
肥満になりやすい
孤食・子食では、どうしても子どもが好きな食べ物、つまり脂質や糖質が多いものに偏りがちです。それが続くと、栄養が偏って生活習慣病のひとつである肥満を引き起こす可能性があります。肥満になると風邪を引きやすくなったり、体調を崩しやすくなったりと、子どもの健康に影響が出るようになります。
体調不良になりやすい
子どもだけの食事が習慣になると、体調不良を訴える割合が高いという研究結果が報告されています。初めて目にした食べ物に対して子どもは「食べられるのかわからない・・・・・・」と不安を抱きやすいので、大人がいないと手をつけないまま食わず嫌いで偏食になっていきます。
好き嫌いが多く、好きな食事しかしないと、子どもに必要な栄養素が足りなくなって、体調不良に陥りやすくなるのです。
不安になりやすくイライラしやすくなる
食事中の会話量が多い子どもは、「子どもだけの食事より大人と一緒の食事の方が楽しい!とても満足!」と精神的に安定していることが研究でわかっています。一方で孤食は、眠れなくなったり、イライラしやすくなったりと、寂しさから心が不安定になりやすいリスクがあります。
社会性や協調性が育ちにくい
食事や会話は、他人との繋がりを育てる重要なコミュニケーションツールです。家族で一緒に食事をする「共食」では、食事をしながら会話を楽しむという経験ができます。しかし、孤食が習慣になっている場合には、食事中に会話する機会がほとんどないため、他人との会話の始め方やコミュニケーションの取り方がわからず、苦手意識を持ってしまう可能性があります。
気を付けるべき7つの「こ食」

「孤食」と「子食」以外にも、子どもの心身の成長に影響を与える「こ食」があります。
6~9個に分けられることが多いですが、この記事では孤食・子食を含め9個で定義します。この段落では残り7つの「こ食」について解説していきます。
固食
固食は、固いものを食べることではなく、固定した食事を意味します。要するに、色んな食材を食べずに、好きな食事しかしないような食生活のことです。
子食の場合は自分の好きな物しか食べなくても注意する人がいないので固食になりやすく、栄養バランスが偏りがちです。
個食
個食は、家族は揃っているものの、各自好きな食事を摂ることです。別名では、バラバラ食とも呼ばれています。
年齢やアレルギー等の事情で分けるしかないこともあるので、必ずしも悪いことではありません。しかし、各自が好きな食べ物しか食べないという食生活になりがちなので、気を付けないと栄養バランスが悪くなったり、好き嫌いが多くなったりする可能性があります。
小食
小食は、食事の量が少なくなる少食(しょうしょく)を意味しています。もともと少食の子もいますので元気に大きくなっていれば問題ないのですが、成長期に無理なダイエットをすると食材から得る栄養量が減り、大きな影響が出ることがあります。
戸食
戸食とは、外食が多い食生活のことです。特に、ファミリーレストランやファストフードが食事の定番になると、野菜不足で栄養が偏りがちになったり、塩分・糖分・脂質過多で肥満になったり、濃い味付けに慣れて味覚の発達に影響が出たりする可能性もあります。
粉食
粉食とは、米ではなくパンや麺類などの小麦をよく食べる食生活のことです。
柔らかい食品が多いので、顎が正しく成長しづらくなります。また、パンやラーメンは主食だけで食事が完結することが多いので、副菜が摂りづらく、栄養バランスが悪くなりがちです。
濃食
濃食は、味が濃い食事のことです。外食中心の「戸食」とも共通しますが、味が濃い食事は塩分や糖分を多く含みます。味覚の発達に影響が出たり、肥満や生活習慣病を引き起こす原因にもなります。
虚食
虚食は、何も食べない、食欲がないことを意味しています。虚食は、栄養不足になりやすく、症状が深刻化すると摂食障害といって、食べることができない状態になる場合もあります。できれば家族揃って、朝昼晩の食生活のリズムを整えていくことが大切です。
頻度ではなく、家族の時間を楽しむことが大切

孤食・子食の改善策として、「一緒にする食事の回数を増やしましょう。夜に食事ができない場合には、朝食を一緒にするようにしましょう」といった対策が提案されがちです。
しかし、生活スタイルによってはどうしても無理なこともありますよね。それに、肥満や体調不良を避けるには栄養バランスを考えた食事を用意することで解決できます。
そして、心の問題に関しては、重要なのは必ずしも頻度ではありません。毎日一緒に食事をしても、会話がなく楽しくなければ孤食と同じことです。
食事回数を増やすよりも、家族で食事する時には、楽しむことが大切。一緒に食べる頻度が少なくても、たまに家族でする食事が楽しい時間であれば、子どもはその時間を待ち遠しく思い、不安になることも少なくなるでしょう。
子どもに孤食をさせることに罪悪感を持つのではなく、家族の食事時間をみんなで楽しむことに気を配ってください。
研究論文:大人と一緒の食事が子どもの食意識・食態度・食知識に及ぼす影響
文部科学省スーパー食育スクール事業の結果から
記事監修:林 徹(歯科医、はやし歯科医院院長)

三重県津市 高茶屋小森町356-2林歯科ビル1F
059-234-0118
https://hayashi-dentalclinic.net/
小さなお子様からお年寄りまで、幅広い層の患者さまに信頼していただける医療を提供することを心がけています。














