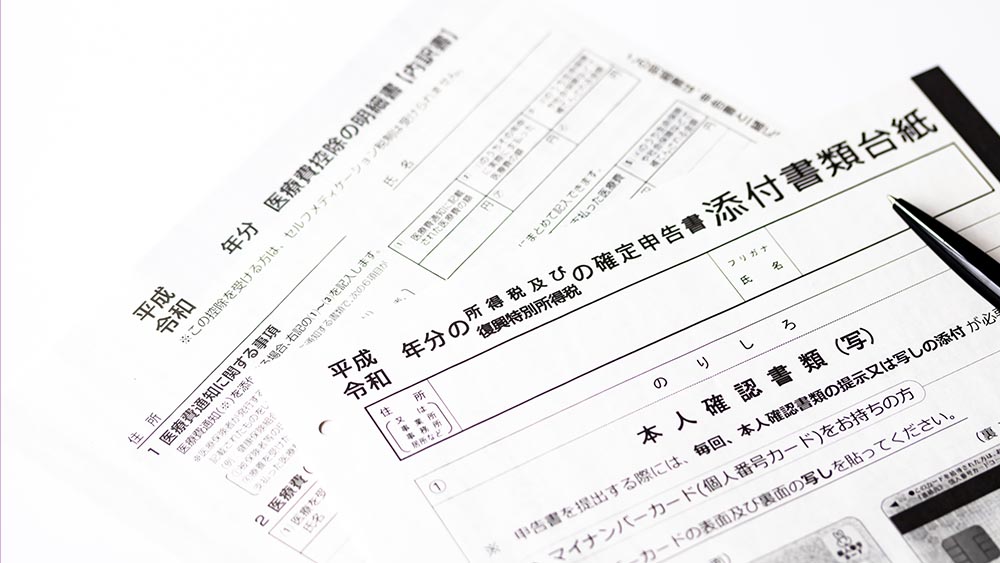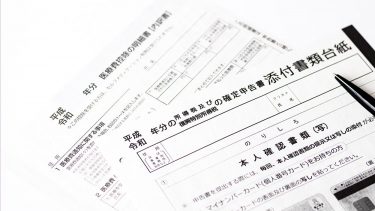みなさんは、医療費控除をしていますか?
確定申告をすることになるので、会社員の方で確定申告の不要な方にとっては、ちょっと面倒に感じるかもしれません。それでも、年によっては医療費が大きくなってしまうことも、ありませんか?案外、ひとり分でも医療費は嵩みますし、家族全員となれば、なおさらですよね。
ある基準額を超えた医療費分を、所得税の税率が掛けられる対象の金額から差し引くことができます。これによって税金が抑えられるので、節税になるのです。
今回は医療費控除について、わかりやすく説明します。
目次
医療費控除について、おさらいしましょう

医療費控除とは、1年間の医療費が多くかかった人の税金を減らしてあげようという制度です。
1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費の総額が、一定額を超えた場合に、確定申告で医療費控除を申請すると、税金を低くすることが出来ます。
具体的には、「医療費控除額」を課税所得額から差し引く(所得控除)ことができます。
医療費控除額は、以下の式で求めます。
「医療費控除額」=1年間の医療費総額-保険金受け取り額-10万円(総所得額が200万円以下の人は、総所得額の5%)
※ただし上限は200万円まで
上記の計算結果がプラスになる場合は、医療費控除の対象になるということです。「医療費が10万円を超えると医療費控除の対象になる」と聞いたことがあるかもしれませんが、これは保険金の受け取りがなく総所得額が200万円を超える場合の計算式が「1年間の医療費総額-10万円」になるためです。
身近な病気やケガでも、医療費は意外とかかる!
会社員時代のこと、ある年に私は歯科での虫歯治療で保険の効かない材質のかぶせモノ(1本につき10万円)を選び、2本治療し、歯科治療費に20万円かかりました。風邪の治療費などを含めて、この年には22万円ほどの医療費がかかりました。
「医療費控除額」は、上記の式で算出すると、保険金は受け取っていないので、22万円-10万円=12万円です。
確定申告で医療費控除をしたところ、5万円ほどの還付金が、指定した銀行口座に振り込まれていたように記憶しています。
確定申告に必要な書類や申請期限は?
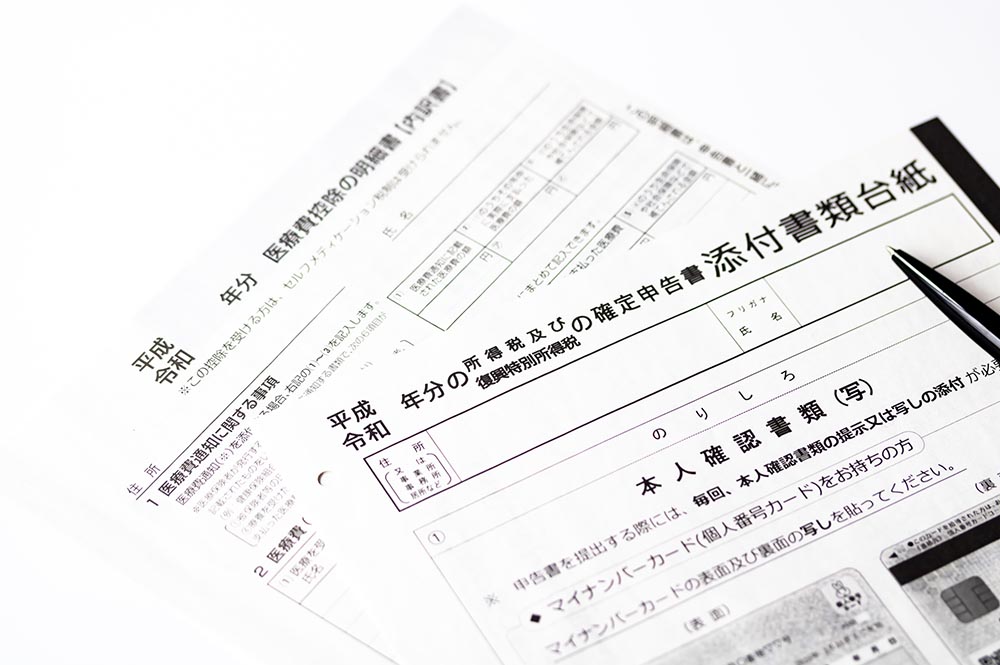
以前は医療機関の領収書の添付が必要でしたが、2017年度分からの確定申告では「医療費控除の明細書」のみあれば良く、領収書の添付は不要となりました。だたし、領収書は5年間保管する義務があります。
また、一般に確定申告は3月15日までという期限がありますが、医療費控除など会社員の還付申告の確定申告は、5年間有効です。2019年の医療費控除なら、2024年12月末まで提出できます。
医療費控除の対象にならない治療もある?
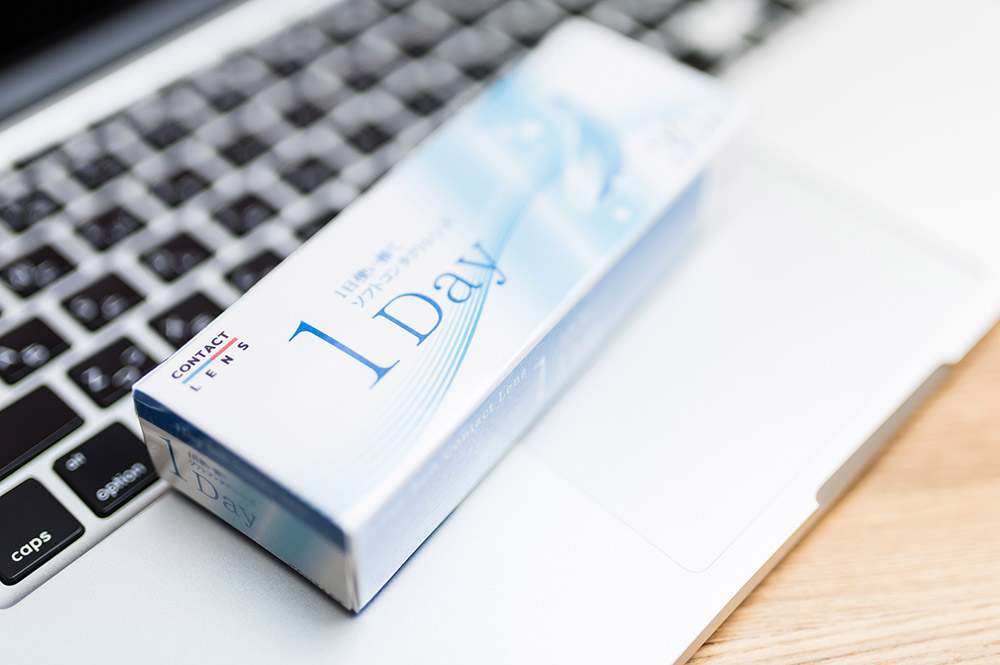
案外大きな節税になる医療費控除ですが、なんでもかんでも医療費控除の対象になるわけではなりません。医療費控除と認められるものと認められないものがありますので、簡単にまとめました。対象になるのは、「医師による診療又は治療の対価」「治療に必要な医薬品購入の対価」が基本です。
控除の対象になる例
健康保険で治療した代金はもちろんですが、健康保険外での治療も対象になるものがあります。インプラント治療や不正咬合による歯列矯正治療も医療費控除の対象です。眼科では、レーシックによる視力矯正も対象です。通院や入院のための医療機関までの交通費も対象になります
控除対象にならない例
美容目的の治療は医療費控除の対象から外れます。審美歯科治療代、美容整形代は対象外です。疲労回復を目的として受けたマッサージやビタミン剤の購入費なども対象から外れます。また、眼科のコンタクトレンズ代も対象外となります。
詳細は国税庁HPで確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
ご存じですか?もうひとつの医療費控除「セルフメディケーション税制」

2017年から医療費控除の特例としてスタートした「セルフメディケーション税制」。ドラッグストアなどで購入した市販の風邪薬や胃腸薬の代金が一定額を超えた場合に、確定申告で税金を低くすることができる制度です(所得控除)。
具体的には、1年間の市販の薬代総額が12,000円を超える(ただし上限は88,000円)と申請ができるので、医療費控除よりも垣根が低く、対象になる方が多くいるのではないかと思います。
政府は、風邪などの重篤ではない病状の場合は、病院にかかるのではなくて、市販薬を服用するなどの自己ケアを推奨していて、この新しい税制を打ち出しました。膨らむ医療費を削減することが目的です。せっかくの税制優遇策ですので、該当するのであれば、利用したいですよね。
確定申告に必要な書類や条件は?
セルフメディケーション税制の医療費控除を受けるには、条件があります。
日頃から自身の健康管理に努めている、という姿勢が求められるのです。
とりわけ難しいことではありません。
以下に挙げる書類を「健康に向けて一定の取組み」の証明として添付します。
1特定健康診査(メタボ診断)または特定保健指導を受診した領収書もしくは結果通知表
2予防接種(インフルエンザ、定期接種)の領収書もしくは予防接種済証
3勤務先で実施する健康診断の結果通知表
4市区町村国保等が実施する健康診査などの領収書もしくは結果通知表
5市区町村が健康増進事業として実施するがん検診の領収書もしくは結果通知表
医薬品を購入したレシートを保管して年末に総額を出してみましょう。対象商品は、1,700品目にも上ります。レシートに☆などのマークが入っていますので確認してください。控除申請には、対象の医薬品の購入履歴をまとめた明細書を記載して、確定申告時に提出します。ドラッグストアなどのレシートは提出の必要はありませんが、5年間は保管の義務があります。
セルフメディケーション税制の明細書は以下からダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf
なお、先述の「医療費控除」との併用はできません。医療費控除の額に達しない場合に、セルフメディケーション税制を申請すると良いと思います。
まとめ
医療費控除もセルフメディケーション税制も、自分一人にかかった費用だけではなく、家族全員の医療費を合算して申告できます。家族全員となると結構多額になることがあります。面倒だからと申請しないのは、もったいないです。共働きの夫婦では、家族分をまとめてどちらかが申請すれば良いので、家計を預かっている側がまとめて管理していくのもいいですね。しっかりと節税に役立てていきましょう。