
VUCA(ブ―カ)という言葉を耳にしたことがありますか。
ビジネス用語として最近よく使われているのですが、
- 変動制(Volatility)
- 不確実性(Uncertainly)
- 複雑性(Complexity)
- 曖昧性(Ambiguity)
の頭文字をとった略語です。
新型コロナウィルス感染症の世界的な流行や、河川氾濫をもたらすような豪雨など、私たちは想像もしていなかった未体験のことに直面しています。
このような疫病や災害といった環境の変化のほかにも、新しいシステムやしくみが次々に誕生していて、既存のやり方では通用しなくなっています。今までのビジネスモデルや考え方、価値観が通用しない時代だと言われます。
将来私たちを取り巻く社会がどう変わっていくのかは、誰にも予測できません。
だからこそ、これからの時代にはどんな局面にも柔軟に対応できる人材が重要です。
ひとつの業務のプロではなく、幅広い知識を備えて、総合的な判断ができる人。ひとつのチームではなく、複数のチームでそのスキルを活かせる人のニーズが高まっています。
厚労省もそんな「働き方改革」の流れを後押ししており、2020年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(※)を改訂時に、副業・兼業についての記述を「原則禁止」から「原則容認」へ変更しました。
いきなり副業自由とはいかなくとも、まずは「社内副業」を取り入れる会社が増えてきています。
今回は「社内副業」がなぜ注目されているか、そのメリットはなにかを見ていきたいと思います。
※厚労省 副業モデル就業規則
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
目次
副業と社内副業の違いは?
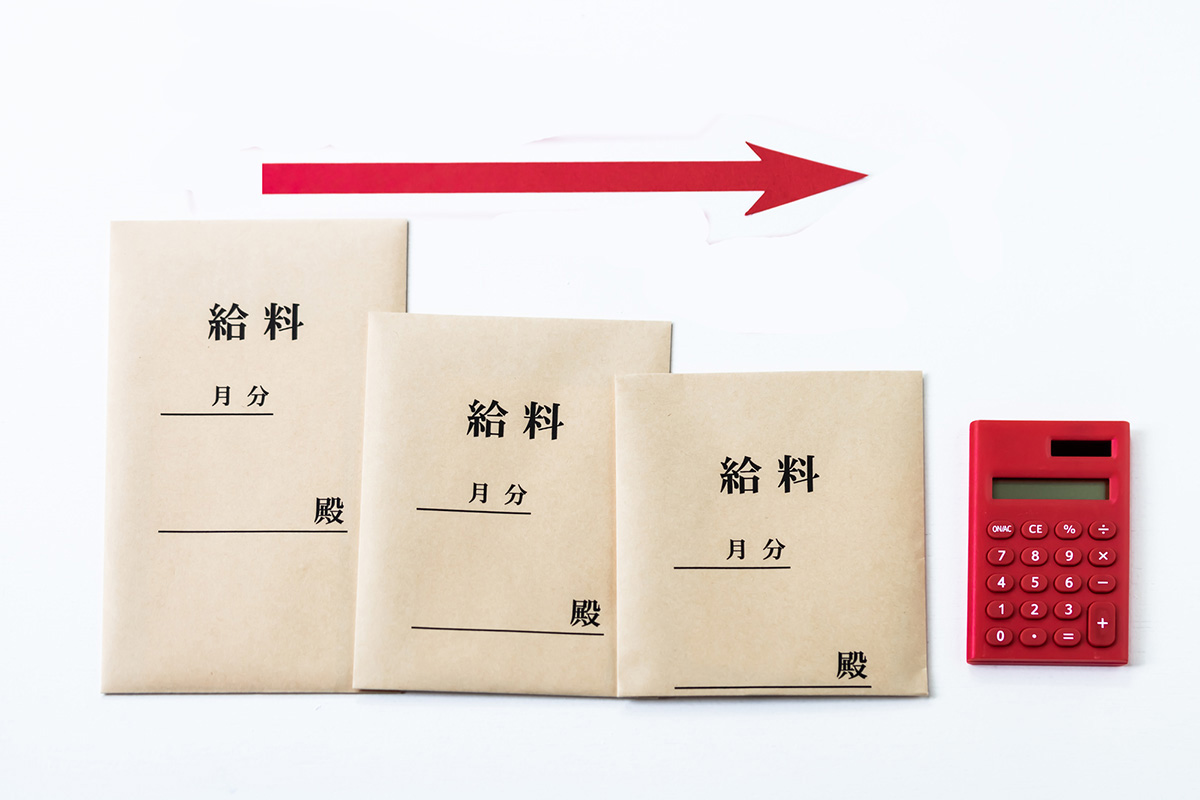
一般的に「副業」とは、“本業を持ちながら勤務時間外に別の仕事をする”というスタイルです。
企業に勤める傍ら、趣味や特技を生かして教室を開く(英会話や生け花など)、現職の技術や専門性を生かして講演や執筆活動をする、という働き方です。
それに対して「社内副業」とは、自分が勤務する会社内で本業となる部署やプロジェクトに属しながらも、別の部署やプロジェクトで本業とは違う業務に携わることです。
気になる報酬は?
多くの企業では、「所属している部署(本業)の給与内で、勤務時間を社内副業に割り振っている」という定義です。つまり、社内副業をしても給与は増えず、現状のままとなります。
本業の時間が減っているので「タダ働き」ではありませんが、社外で収入を得る「副業」とは異なります。
しかしサイバーエージェントのように、「本業の業務以外の仕事を時間外に請け負う」という位置付けにして、通常の給与以外の報酬を得ることができる制度を導入している企業もあります。
社内副業のメリット

本業に携わる時間を減らして副業として他業務に関わる――。副業が失敗するともちろん痛手ですが、実は企業側・社員側ともにメリットがある仕組みです。
ローリスクでチャレンジできる
現在の所属部署で与えられている業務で、能力を生かし切れている、モチベーションを高く保てていると言い切れる人ばかりではないでしょう。
社内副業制度によって、社員は離職することなくやりたいことにチャレンジする機会を得られます。そして企業側は、能力が生かし切れていない社員に、本業とは違う立場でのキャリア形成の機会を与えることができます。
双方にとって、ローリスクだと言えるでしょう。
業務改善、効率化できる
社内副業によって他業務に関わることで、社員はより広い視点を持つことができます。これまで見えていなかった課題が見つかるなど、業務改善につながる気づきもあるでしょう。
企業側も、俯瞰的な視点を持てる社員の存在は貴重。部署を横断しての業務の改善や効率化が期待できます。
まとめ
社内副業は、社員としてキャリア形成につながり、企業としても組織の活性化と課題解決につながる制度であるといえるでしょう。業務量の調節や時間管理などの制度運用がしっかりと機能することが前提ですが、チャレンジする価値はあります。
他人事としてついスルーしてしまいがちですが、勤務先に制度が用意されているのであれば積極的に利用してみることをおすすめします。













